- イベント
みんなで巻こう!「節分巻寿司教室」開催 広島企業コラボレーション特別企画 第2弾
2024年01月15日
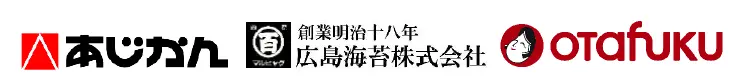
株式会社あじかん(代表取締役 社長執行役員:足利 直純)、広島海苔株式会社(代表取締役社長:國光 芳弘)、オタフクソース株式会社(代表取締役社長:佐々木 孝富)では、節分を前に、合同で巻寿司づくり教室を開催いたします。
いずれも広島市西区商工センターに拠点を置く食品企業3社それぞれの製品を使用して、参加者の皆さまに2種類の巻寿司をつくっていただきます。
- 日時
-
2024年2月1日(木)11:00~14:00
- 場所
-
Wood Eggお好み焼館 3階 キッチンスタジオ
- 参加者
-
(事前にお申込みいただいた)10組20名様
- ※1月5~14日に3社の公式Instagramをフォローし、各社の投稿のいずれかにコメントをくださった方の中から抽選で決定しました。募集は締め切らせていただきました。
- 内容
-
- 巻寿司豆知識講座
- 巻寿司づくり体験
- 1福を呼ぶ!具たっぷり恵方巻
- 2鬼にカツ!金棒巻
講師:株式会社あじかん 社員
- 試食
巻寿司、海苔とチーズのミルフィーユ、ピクルス、たこ焼すまし汁、GOVOCE※、ごぼう茶
- ※あじかんの独自技術で焙煎したごぼうを使用。カカオを一切使用せず、見た目や風味、くちどけはチョコレートのような新スイーツ

- 株式会社あじかん(営業推進部 田中)
TEL:082-277-9047 MAIL:m-tanaka@ahjikan.co.jp
- 広島海苔株式会社(営業部 小松)
- オタフクホールディングス株式会社(広報部 鍵村)
TEL:082-553-9961 MAIL:ota-pr@otafuku.co.jp
取材にお越しいただける際は、オタフクホールディングスへご一報くださいますようお願いいたします。
巻寿司の歴史
巻寿司は江戸中期の1750~1776年の間に生まれ、1783年頃に一般化したと考えられています。200年以上も愛され続ける歴史のある食べ物です。誕生して間もないころは、薄焼玉子、浅草海苔やワカメ、竹の皮で巻いた巻寿司も多くありました。
かんぴょうの細巻が「海苔巻」として江戸(東京)で刊行された書物に残されているように、海苔で巻くようになったのは江戸が発祥と考えられています。関西で刊行された書物には、複数の具材を巻く太巻きが紹介されています。この頃から関西では豪華な太巻が、江戸ではすっきりした細巻が好まれていたようです。
大正時代になると、巻寿司は家庭でも作られるようになります。昭和初期の頃には、年中行事やお祝い事のあったときなど、家族にとって特別な「ハレの日」に作る、ご馳走メニューのひとつになりました。そのころ大阪では、恵方を向いて巻寿司を丸かぶりすると幸運に恵まれるという「幸運巻寿司」なるものが宣伝されていました。この風習は戦争などの影響で一時は廃れますが、1970年代後半に大阪海苔問屋協同組合の行ったイベントを契機に復活し、関西地方に定着しました。さらに2000年頃からは、節分にスーパーやコンビニで「恵方巻」として販売されるようになり、急速に全国へ広まりました。
参照:あじかんコミュニティサイト「MAKIZUSHI倶楽部」(https://makizushi-club.com/)
教室で使用する食材と各社紹介
玉子焼・おぼろ・椎茸・干瓢・かに風味蒲鉾、メンチカツなどの具材 / 株式会社あじかん
あじかんは、足利政春が京都の玉子焼の老舗「吉田喜」で修業を重ねた後、のれん分けを許され、1962(昭和37)年に広島市で創業しました。弁当、惣菜、半調理製品などで使用する、玉子焼、椎茸、干瓢などの寿司食材、かに風味蒲鉾、ごぼう惣菜などの業務用食品を製造、販売しています。特に厚焼玉子やきんし玉子をはじめとする玉子製品は約450アイテム、チルドでは全国シェアのトップクラスであり、多くの方にお召し上がりいただいています。
また、日本の伝統食として巻寿司の魅力を伝えるため、その歴史や節分の由来などとともに作り方の教室を各地で開催したり、SNSを中心に巻寿司に関するさまざまな情報を発信したりしています。
海苔 / 広島海苔株式会社
広島海苔は、1885(明治18)年に國光百次郎が海苔問屋として創業しました。海苔や魚を買い付け、大八車で売り歩く行商をしていたときに、軽くて運びやすく、日持ちが良く、栄養もある海苔は、大きな商いになると直感したことが原点です。
江戸時代、海苔は幕府の財源を支える専売品であり、生産を許されていたのは江戸と広島のみでした。江戸後期に専売制が廃止されてからも、広島の海苔養殖は大きく生産を伸ばし、明治から大正中期にかけて西日本で一番の産地として発展しました。
広島の味として長年愛され続ける「かき醤油味付のり」をはじめ、日本の食卓に欠かせない海苔を、加工・販売しています。
寿し酢 / オタフクソース株式会社
オタフクソースは、1922(大正11)年に佐々木清一が卸小売業で創業し、1938(昭和13)年から酢の製造を始めました。酢はソースよりも歴史がある商品です。「寿し酢」は1955(昭和30)年から販売しています。広島市内の寿司店を訪ねるうちに「職人が変わると、シャリの味も変わってしまう」という相談を受け、いつも同じ味を安定してつくることができるように、合せ酢として調合したのが誕生のきっかけでした。
現在は、三原市大和町の工場で醸造しており、深堀井戸から汲み上げた軟水でつくる酢は、旨みと甘みのバランスがよく、まろやかな口あたりが特長です。



