- 食文化の普及
オタフクソースのお好み焼にかける熱い想い
すべての世代へ、そして世界へ。お好み焼文化を広めたい
2025.3 | 食文化の普及
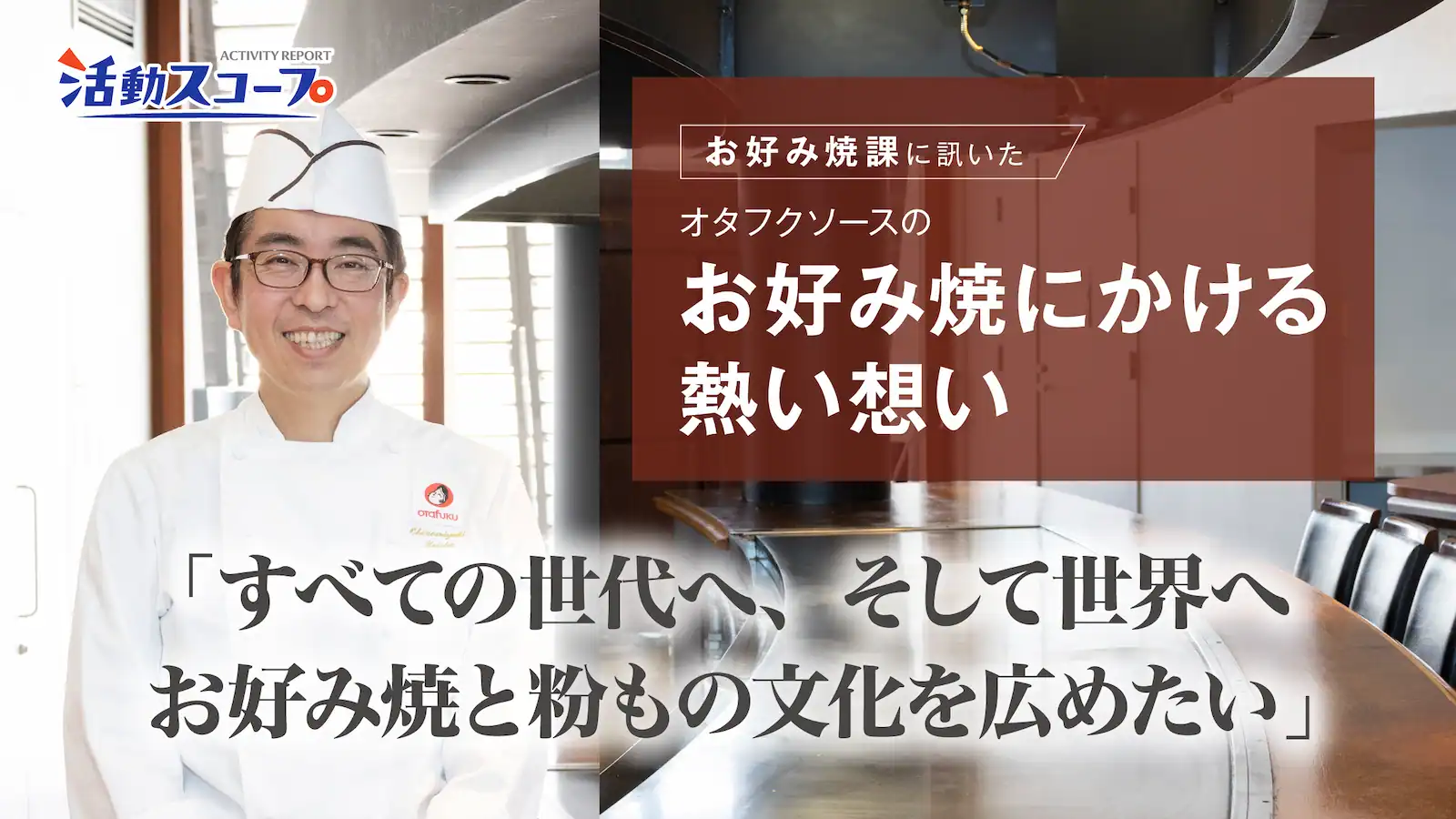
Otafukuグループのさまざまな活動とそこに携わっている人をレポートする「活動スコープ」のコーナー。第一回は「お好み焼課」の春名陽介さんをインタビュー。「お好み焼課」という部署が、どのような目的で発足し、何を目指しているのか。春名さんのお好み焼に向き合う姿勢は。
「お好み焼課」の活動の中心拠点、広島市西区の本社に隣接する「Wood Egg お好み焼館」で取材しました。
お好み焼や粉もの文化を広めるため
1998年に「お好み焼課」を発足
「お好み焼課」は、1998年に発足した、お好み焼の普及や研究を目的とする部署です。一般の方に向けたお好み焼教室や、お好み焼店を開業されたい方への研修の実施、小学校での食育授業、学園祭やイベントの支援、お好み焼体験スタジオの運営、イベントでのお好み焼の実演提供やメニュー作成、新しいメニューの研究・開発・提案など「世界にお好み焼や粉もの文化を広める」を合言葉に、多彩な活動を続けています。
オタフクソースのメイン商品であるお好みソース。それをたくさんの人々に知ってもらい、親しんでもらいたい。そのためにも「お好み焼」の普及は必要不可欠です。お好み焼に向かい合い、熱い情熱を注ぎ続ける「お好み焼課」の活動について、同課課長の春名陽介さんにお聞きします。
各社員が抱いていた熱い想いを
企業の公式なメッセージへと設定
―「お好み焼課」が誕生した背景を教えてください。
春名:私が入社したのは「お好み焼課」が発足した6カ月後ですが、その数年前から、お好み焼店様を訪ねて情報を提供したり、意見をお聞きしたりという活動を行っていたそうです。また、同時期に全国の量販店様の店頭にホットプレートを持ち込ませていただき、100万人規模でお客様に試食を提供をするという活動実施しており、私は入社直後にどちらも経験しました。現場を自分の目で見られる貴重な機会でした。
これらの活動は、以前から営業やマーケティングのスタッフがやっていたことですが「お好み焼課」ができたことで「お好み焼を全国に広める」ことを定義したものと思います。
オタフクソースには、従来からお好み焼に対する熱い想いを持っている社員が多く、それを企業としての永続的なメッセージに変えた意味は大きく、私もその部署に配属されたことで、背筋の伸びる想いでした。

幸せな記憶やストーリーとリンクする
お好み焼を囲む時間
―設立初期の活動は、何から始めたのでしょうか。
春名:お好み焼を全世代に広めることを目標にし、「食べる機会が少ない世代はどこか?」を考えました。そこで当初は、高齢者施設と幼稚園をキャラバンカーで回ることから始めました。お好み焼を口にする機会が減ってしまった高齢者の方にもう一度味わっていただく。また、幼稚園の子どもたちにとっては、はじめてのお好み焼になることも多いので「こんな料理があるんだよ」と知ってもらおうと。
反応はすごかったですね。高齢者の皆さんにとって、お好み焼は幸せな記憶とリンクしているんですよ。働いていた頃の風景とか、家族と一緒に食べた時間とか、誰かのために焼いていた思い出とか、涙ながらに話してくれる方もいました。
子どもたちも「はじめて食べたけどおいしかった」「お父さん・お母さんに作ってもらいたい」と喜んでくれました。お好み焼って、ストーリーと一緒にある食べ物なんだと、その時はっきりと感じましたね。お好み焼を広める活動の意義を感じることができました。
毎日食べても飽きない
公式お好み焼レシピを考案
―初期に苦労した思い出はありますか?
春名:「オタフクソースとして一番おいしいお好み焼」の焼き方を統一したことです。それ以前は、社員によって焼き方は異なっていました。どれもがその人の主観で、それぞれが「自分のやり方が一番おいしい」と思っていました。基準を設定するためにお好み焼を作る過程、すべての項目についてベストな状態を再検証しました。例えば広島お好み焼の場合、生地の上にキャベツを乗せるのはなぜか。生地の上に削り粉をしないのはなぜか…という感じです。結果として「毎日食べても飽きないお好み焼」をコンセプトとして、自然の削り粉や昆布粉を使用した、味付けをあっさり目にしたレシピを決めました。
その活動の発展形として、2006年には「お好み焼士」という社内資格制度も生まれました。筆記試験と実技(お好み焼を焼く)試験が年1回実施されており、資格取得は昇格要件のひとつにもなっています。

教室や研修を通してお客様と直接交流
そこから得られるものは大きい
―お好み焼の教室も長年手掛けているそうですね。
春名:個人向けとプロ向けの2種類がありまして、いずれも「お好み焼課」の発足以前から続いている活動です。一般の方向けの「お好み焼教室」については、現在は弊社の施設内(広島・東京)での開催を中心にしていますが、当初はホットプレートを公民館などに持ち込んで出張教室をしていました。ご自宅でおいしいお好み焼を焼けるように、食卓に1回でも多くお好み焼が並ぶ機会が増えるようにという想いからですね。今のように調理動画などが普及していない時代ですから、かなり好評をいただきました。現在は広島駅ビル内に、来店して気軽にお好み焼づくりを体験できる「OKOSTA」という施設(要予約)も運営しています。
そして、これからお好み焼店舗を開きたいという方向けの「お好み焼研修センター」を東京・大阪・広島・福岡で運営しています。お好み焼の基本の焼き方や、色々な焼き方のバリーエション、鉄板焼メニューなど、理論を含めてみっちりと3日間。経営面の講習も実施します。卒業生には今では有名店として知られているお好み焼店店主様もいらっしゃいます。受講された方が実際に店舗を開店する際には、私たちも応援で店舗に入らせていただくこともありますが、この経験はお好み焼店様の想いを理解し、現場にとって何が重要かを肌感覚で感じられるとても重要な機会となっています。
「お好み焼課」の社員は、生活者やお好み焼店の店主様など、お客様の声を常に聞いているがゆえに、最近では、新製品の開発や商品の仕様変更に対する意見などを、社内から求められることも増えてきました。お客様と触れ合う立場だからこそ、可能となる役割もあると思っています。
お好み焼は世界を救う!?
国内はもちろん、世界へ広めていきたい
―これからの目標を教えてください。
春名:まずは国内ではお好み焼を「国民食」にしたいですね。まだそのレベルまでは至っていないと思っていて。鉄板を囲んで家族や友人がワイワイと楽しめる食事、それがお好み焼です。コミュニケーション食という利点がもっと浸透して、すべての世代の食事において、お好み焼を食べる回数を増やしたいです。
また、お好み焼って栄養バランスの良い食べ物だということをもっと広めたい。野菜も肉も炭水化物も入っていて、それが混ざっていることにも大きな意味があります。子どもたちが食卓に並んだ料理で苦手な具材だけを残したりしますが、そうすると栄養バランスは崩れてしまいます。でも、お好み焼は半分残しても、混ざっているから栄養バランスは同じまま。だから最強の食べ物なんです。これをもっと知っていただきたいですね。
もう一つの目標は、世界で「OKONOMIYAKI」として広まることです。お好み焼は終戦直後の物がない時代に、小麦粉を分け合って、そこに入手可能な具材を乗せて焼いたことから発展していますから、これからの世界で想定されている、食料不足という課題にも対応できる料理だと思っています。
今、海外向けに、それぞれの国の条件や嗜好に合わせたお好み焼のレシピを作っています。お好み焼は、水も大量に使いませんし、小麦粉にその土地で使える素材を混ぜて焼けば、どこでも作ることができます。アフリカならタロイモやヤムイモも使えます。先日、ウクライナから来た方たちにジャガイモと鶏肉を具材としたお好み焼を提供して喜んでいただきました。宗教的に豚肉が使えない地域も、替わりに鶏肉を使いハラール認証ソースを使うことで、ムスリムフレンドリー対応にできます。
古来から伝わる「粉を練って焼いて食べる」という文化が、「OKONOMIYAKI」となって世界に広まることで、SDGs的にも意味があるし、私は本気で「世界を救う」とまで思っています。


6歳の頃、父と訪れた店舗でお好み焼に初めて触れ「こんなに美味しい食べ物があるんだ」と感動し「お好み焼店主になりたい」という夢を持っていました。就職活動時にオタフクソースの求人票を見つけ「大好きなお好み焼に関わりたい」と応募し「お好み焼課」に配属されたことで、さらに運命を感じました。
仕事をする上で心掛けているのは、上司から教わった「相手の立場に立って考える」です。現在は、研究も兼ねて、外食や自身で焼くなど、ほぼ毎日お好み焼を食べ続ける「お好み焼中心の日々」を送っています。プライべートでは、お好み焼に関わるとついつい仕事モードになってしまうので、家族に注意されてしまいます(笑)



